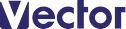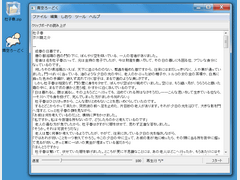あるとき「文書作成やメールの入力、Twitterでのつぶやきなどで入力間違いを減らしたい」と考えた。そのための手段として、目視チェックに加え、入力した文の読み上げによる確認を行ってみた。すると、文を声に出して読むことが誤りの発見に意外に有効なことがわかった。そこで「音声読み上げソフト」を利用して文の読み上げチェックを行おうと考え、出合ったのが「青空ろーどく」だ。いくつかある「音声読み上げソフト」の中で「青空ろーどく」を選んだ理由は、筆者が20年近く「青空文庫」のファンであるためだ。普段は「青空文庫」に対応したビューアを利用し、読みたい文学作品を文庫本のような体裁で楽しんでいるが、文学作品を音声で聞き、情景を浮かべながら楽しみたい場合や、目が疲れているときなどもある。「青空ろーどく」は、そんなときに便利に使えるかもしれないと考えた。
インターネットの電子図書館である「青空文庫」には、作者の死後50年が過ぎて著作権保護期間が満了した文学作品や、著作権者が「自由に読んでかまわない」とした文学作品が、プレーンテキストやXHTML/HTML形式で公開されている。もう少し正確にいえば、プレーンテキストでは表現できない日本語組版要素が、書式を定めた注記という形で簡易的にマークアップされており、その形式を「青空文庫形式」と呼んでいる。
「青空ろーどく」は、「青空文庫」からダウンロードしたテキストファイルを読み込み、合成音声で読み上げてくれる。ZIP形式で公開されている「青空文庫」のテキストファイルも、解凍する必要がなく、そのまま読み込んでくれるので便利。ルビありテキストを読み込むと、ルビや傍点、注釈用の記号を自動で除去してプレビュー表示してくれる。ファイルの読み込みに要する時間はファイルサイズに比例するが、芥川龍之介の「杜子春」でも数秒程度と、ほとんど気にする必要はない。
テキストが読み込まれた状態で画面右下の「スタート」ボタンを押すと、合成音声で読み上げてくれる。読み上げている個所はハイライト表示されるため、朗読を聞きながら読み上げ位置を追うことも容易。テキストの該当個所をクリックすると、その位置で音声が再生されるため、戻ったり、進めたりといった、聞き直しもできる。
画面下部の「速度」で、読み上げ速度を調整することも可能。速度の初期値は100で、スライダーをドラッグして50〜300の間で設定できる。
読み上げ精度は高く、たまに漢字の読み間違いはみられるものの、個人的には許容範囲内だ。気になる場合は、読み間違いをする漢字をひらがなに直すなど、編集画面で修正すればよい。句読点や改行時の無音間隔(待ち時間)などの設定も可能だ。
また「しおり(ブックマーク)」機能を備え、本文の好きな位置に3ヵ所までしおりを挟み、中断していたところから朗読を再開できる。
読み込んだテキストファイルを、WAV形式やMP3形式の音声ファイルとして出力する機能もある。その際、読み上げ速度は、「音声ファイルの出力」を実行したときの設定速度となる。なお、MP3形式の音声ファイルとして出力するには、別途、MP3エンコーダ「LAME」が必要となる。
前述したように、作成した文書やメールの文面などを「青空ろーどく」に読み込ませ、読み上げさせてエラーチェックを行える。これがとても便利で、白状すると、「青空文庫」の作品を鑑賞する用途よりも、作成した文書やメールの文面、Twitterへの投稿など、さまざまな文の確認に「青空ろーどく」を用いている。
本音をいえば、「青空文庫」の文学作品を音声で楽しむには、プロの「語り手」のような声で聴きたい。「青空朗読」というサイトでは、「青空文庫」の作品の一部(約250タイトル)を朗読したデータが公開され、ブラウザで聴くことができる。こちらもお勧めだ。とはいえ、「青空文庫」で公開されている作品は膨大で、「青空朗読」ですべて網羅できてはいない。「青空ろーどく」の活躍する場面は多く、これからもうまく活用してゆきたい。
なお、「青空ろーどく」を利用するには別途、オープンソースの日本語形態素解析エンジン「MeCab」をインストールする必要がある。Windows版のパッケージをダウンロードして実行すると、コンパイル済みのIPA辞書とともに「MeCab」がインストールされる。
合成音声の再生には「AquesTalk(アクエストーク)」を利用するが、「AquesTalk」は「青空ろーどく」に同梱され、自動でインストールされるので、別途、音声合成エンジンを入手する必要はない。