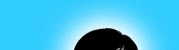
| ベクターTOPへ |
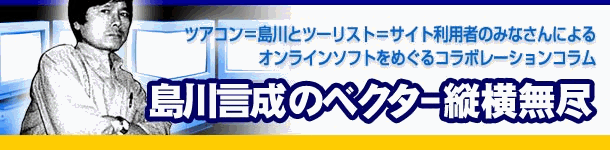
たぬきさんからメールが届いた。長文メールだったので要旨をまとめてみた。
続いて、やはり続行中のソフトの適正価格問題に関してだ。このところ「ソフトは無料という風潮」が議論されるようになった。それを提起してくれたビッグゲートさんの功績は大(笑)。たぬきさんは、同じ風潮について以下のように書いてきた。 「ソフトウェアにお金を払いたくないという風潮には、デバイスドライバのダウンロードサービスも影響を与えているかもしれません。ハードウェアを生かすも殺すもドライバ次第なのですが、現在は無料で当然という状態です」 なるほど、これは一理ある。パソコンの周辺機器は多様である。が、プリンタやデジカメを購入しても、同梱されているデバイスドライバの価格は通常状態では見ることができない。大半のユーザは無償だと考えているはずだ。だが、実際には違っている。それぞれのハードメーカーに確認すれば理解できるだろうが、デバイスドライバが収録された媒体(FD/CD/DVD)などが、ユーザの過失で破損した場合、有償で購入することが一般的だ。ソフトウェアの権利団体は、周辺機器だけでなく、パソコン本体まで含めて、価格表示方法を見直さねばならないとオレは主張しよう。 さらに、たぬきさんの思い入れ具合が、強く伝わってきた推奨ソフトを紹介しておく。 「私がほかの人に推奨したいソフトは、地味なユーティリティですが、「RealSync」です。Windows用のデータバックアップツールで、バックグラウンドで15分おきに動作させて、1GBを超えるデータディレクトリの同期をとってもほとんどフォアグランドに影響がないほどの軽さとスピードは、私の知る限り他に類を見ません。開発者が学生(というより少年か?)であるというのも驚きでしたが、そんなこととは無関係にソフトの仕上がりはすばらしいものです」 ここまでユーザに惚れ込まれたソフトを開発された吉本龍司さんは頭を掻くように(ぽりぽり)。頭を掻くといえば、macさんから、オレにも頭を掻かせるようなメールが届いた。一読して、兜の緒を締めねばならんわいと考えてしまった。 「このコラム、とてもいいです。内容もそうですが、文章がいい。かすかに漂うナルシシズムとストイックさ。ハードボイルドの王道をいくような名文。おいそれとは書けません。きっと、長い時間をかけて、文章を紡いでいらっしゃるのではないでしょうか。こんな素敵な文章、ネットでは初めて見ました」 さきほどのたぬきさんは、オレが、現在の「週刊アスキー」の前身だった「EYE・COM」誌時代の連載をご存知だったが、モノカキという仕事に従事するようになって長くなった。8ビットマシン時代からだ。現在は32ビットから64ビットマシンにシフトしようとしている。macさんは「どうか、長く続けてください」と書かれてきたが、当コラムは“中締め”になるだけだ。アキバ、パソコン、ソフトウェアがある限り、オレの問題意識は続くから、またどこかでお会いできると思うね。 当コラムでおなじみの大嶋和人さんからも、ありがたいメールを頂戴した。 「島川さんこんにちは。9月末で終わってしまうんですね。ってひっくり返して続くこともありですか? 私は、続けてほしいに1票です。おもしろいですから。考えさせられることもあったし、自分が開発している手前、どういうソフトにしたら意味があるのか? というのがつかめそうでした」 大嶋さんのメールには、フリーソフトだけでなく、ソフトウェア全体に関する真摯な見解を読み取ることができた。オレもこれまで何人ものプログラマたちの実態に接してきた。その経験から、極度に冗長的表現を嫌う傾向が強い性格はプログラマに一貫した性格だと考えるようなところがあった。実際、ソフトメーカーのセールスマンの口から、「プログラマは職人ですから、セールスのことなど理解するつもりもありません」と聞かされたこともあった。 そこに、開発に携わっていながら、ヒューマニティに溢れる見識を示してくれた大嶋さんのような人もいるのだと知り、少しく偏見が正されたような気がした。講座を持っている専門学校では、ゲームプログラマのタマゴたちに、「自分の作品を他人に理解できるように説明できないようでは困る」と怒鳴っているが、今後のソフトウェア文化を支える人たちは、かくあらねばならぬと確信している。 いよいよ、来週は当コラムの大団円。ソフトはこんな見方もできるという声は、まだまだあるだろう。 |
|
|||||||