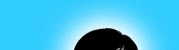
| ベクターTOPへ |
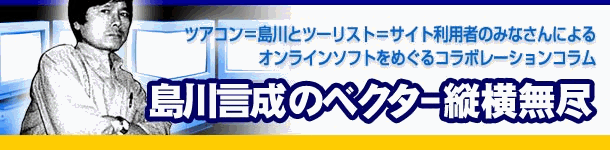
「なんと、私のメールの話題が載ってる! しかも解析や著作権などの話題なのに取り上げてくれた。コラボレーションコラム、メールを出してみて、やっとこの企画の意味を少しわかったような気がします。刺激的です(笑)」 と書いてきたのは、先週登場のたかはし@えかきさんだ。長文メールをありがとう。当コラム、ソフトウェアという距離感を把握できない存在を、あらためてを見直してみようじゃんという趣旨でやっているが、パソコン誌などではやらんこの趣旨を理解してくれた人がまたひとり現れた。うれしいことだなぁ。膨大な数のROM読者がいると思うのだが、ビシバシと「わたしゃ、ソフトってこう考えてるもんね」と書いてきておくれ。 さてと、先週は開発者でもあるたかはし@えかきさんのメールから、ソフトウェアを利用する場合に、必ず意識していなければならない著作権に関してチラリと覗いた。で、この1週間(正確には9月3日)に著作権に関して厳正な措置を求める裁判が提起された。ご存知の人も多いだろうが、以下に概略を述べておこう。 原告はコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)に所属するマイクロソフト、ジャストシステム、クォークインクなどの企業。被告は東京コンピュータ専門学校(学校法人豊樹学園)、東京ゲームデザイナー学院(エッグエデュケーショナルインテリジェンス)、ヘルプデスクの三つの専門学校だ。 被告の三者は、正式なライセンス契約を締結せずに各社のソフトを生徒たちに利用させていたそうだ。事実ならば、これは明らかな違法行為。ソフト不正使用における損害賠償請求金額の算定方法については明らかでないが、今回のケースでは、正規契約した場合の2倍のペナルティを付加され、なんと総額5億7,000万円を請求された。「そんなぁ、2倍はないでしょ」と考える人がいるかもしれないが、鉄道におけるキセル乗車に対する制裁金額からして、妥当な金額だと考えるオレである。ただし、事実を知らされないでソフトを使用していた生徒たちには罪はないし、彼らの学習環境に支障が出ないことも祈りたい。 ちなみにオレが講義を持つゲームクリエイター養成学校の場合、入学式でACCSの久保田専務理事が挨拶されることからも理解できるだろうが、ライセンス契約したソフトを教材に採用している。契約金額は膨大だが、自社の知財特許に厳しい視線をおくる時代、当然の対価を支払わねばならない。 企業のなかには、アプリケーションソフトをCD-Rに焼く行為を当たり前としているところもあると聞く。今回と同じようなケースで社会的に名前が出てしまう以前に、使用許諾契約書の文言を再確認せよと警鐘を鳴らしておく。で、キンコンカンと警鐘を鳴らしてみたわけだが、ソフト販売戦略の具体的な事例を知らせてくれたビッグゲートさんのメールを読んだら、複雑な感慨を抱いてしまった。ちょっと長文だが、これを紹介したい。 「(業務用ソフトのケースでは)中央省庁で採用されたり、大手企業の基幹システムで導入されると波及効果があります。売る側も“XX省で採用され”とセールストークで使います。大手企業で採用された場合、子会社、関連会社、果ては取引先まで同じソフトを買わなきゃならないこともあります。それに付随したサーバやプリンタ、複合機などのビジネスも発生しますから、ソフトを1円で売る、ハードの付加価値としてタダで付ける会社が出てくるわけです。この『ソフトはタダ』という考え方が、著作権侵害の温床になっているんじゃないかと思います。ソフトウェアだけで純粋に商売している会社にとって非常に困った問題です」 売買行為とは、その当事者の一方が、ある財産権を相手側に移転し、相手側はそれに対して対価を支払う契約行為と民法555条は記載している。普通の商品ならば、条文通りだから、余計な説明をするなとなる。が、ソフトはどうだろうか? 大半のソフトは、対価を支払うと同時に「ソフトウェア使用許諾契約」に同意する必要がある。著作権者(開発会社)は、当該ソフトの使用条件を詳細に記述している。 はじめてパソコンを購入した人は、使用許諾契約書の表現を煩わしく感じ、内容の理解はパスして、ひたすら「同意する」状態になっているのではないか。では、何が書かれているのか? ソフトの使用範囲の定義、ソフト複製の可否、ソースプログラムの解析禁止、第三者への譲渡の可否、問題が発生した場合の解決方法など、使用者が配慮しなければならないことが書いてある。皮肉のような表現で申し訳ないが、はじめてパソコンを購入した人程度では理解できないように書いてある(爆)と表現しては言い過ぎか。 ビッグゲートさんが指摘するように「ソフトはタダという考え方」を流布する行為が起きているなら、説明責任を果たさず、ソフトの価値を認めない、仲介業者にも問題があるとしか言いようがない。ソフト会社は「ソフトウェア使用許諾契約」を、誰にでもわかるように記述し、その存在が法的に有効なのだということを、利用者に理解させる努力を怠ってはならんぞという結論になるのであった。 |
|
|||||||